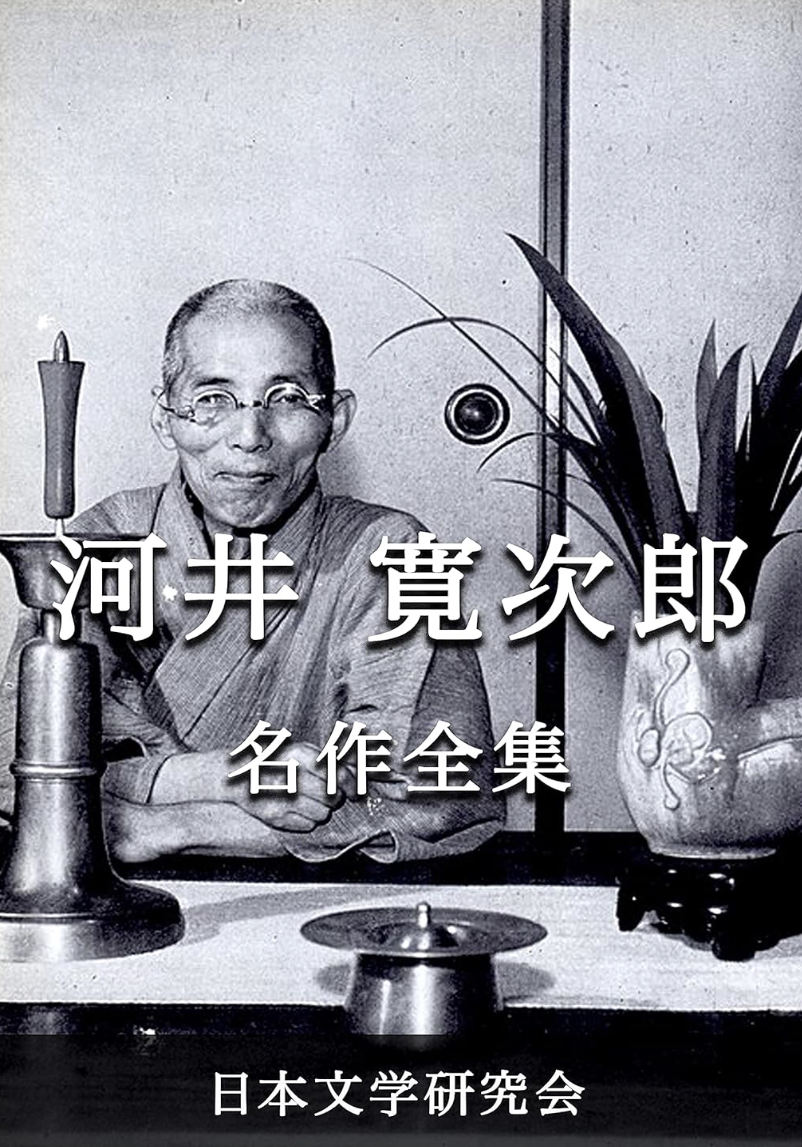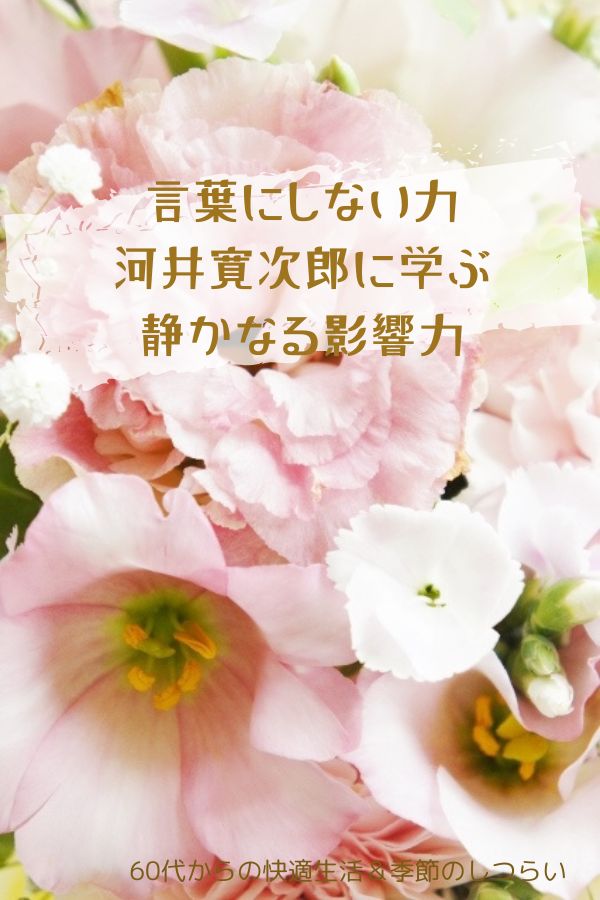
静かなる影響力について考える
河井寛次郎の言葉に、こんな一節があります。
「影響力というのは、さわがぬものである。
静かなる影響力こそ、ほんとうの力だと思う。」
この言葉を初めて目にしたとき、心に静かに残りました。
派手さも主張もなく、けれど確かな輪郭を持っている——そんな印象でした。
仕事がら季節の草花を飾ることを日々の習慣にしています。
器を選び、置く場所を考え、少し背景にも気を配る。
それだけのことですが、空間の雰囲気がやわらぎ、自分自身の気持ちも整ってくるのを感じます。
誰かに見せるためでも、評価されたいわけでもなく、
ただ自分が「整えておきたい」と思うからそうしています。
小さなことが、空気を変える
季節のしつらいは、暮らしの中のごくささやかな工夫です。
花をいける、香りを取り入れる、風の通り道をつくる。
そんな小さなことでも、部屋の空気が変わります。
こうした空間で過ごす時間が、自分の心の状態に静かに影響しているよう。
そして不思議なもので、それはやがて、誰かとの会話や態度、仕事や日々の選択にも、少しずつ反映されていくように感じます。
意図して「影響を与えたい」と思わなくても、
日々の積み重ねや、身の回りのあり方が、無言のまま周囲に伝わっていくことがあるのです。
声を上げずとも伝わるものがある
年齢を重ねると、誰かに強く訴えることや、自分の考えを押し通すことに、以前ほど魅力を感じなくなりました。
それよりも、どんな場所にいても、自分なりの整った時間や空間をつくれることのほうが、よほど力強いことのように思えるようになったんです。
影響力とは、声の大きさや行動の派手さではない。
それが河井寛次郎の言う「静かなる影響力」であり、
私たちが暮らしの中で手にできる、確かな感覚のような気がします。
自分を整えることは、まわりにも波紋を広げる
しつらいを通して空間を丁寧に扱うことは、
言葉にしなくても、自分の内面を表しています。
無理に発信しなくても、誰かに何かを教えなくても、
整った空間や所作が、静かにまわりに作用していく。
声をあげるよりも、何気ないふるまいにこそ、人は触発されるのかもしれません。
ふとしたきっかけで出会った言葉が、暮らしの中で息づいていく。
それが、静かな影響力の本質なのだと思います。
私自身、そうした在り方をこれからも大切にしていきたいです。